Noteステロイドホルモン学会 国内
2025年2月22日(土)にライトキューブ宇都宮で行われた「第32回日本ステロイドホルモン学会学術集会」の資料をオンラインで見つけたので、興味のある部分に目を通してみました。
新しいバイオマーカーの可能性
資料の36ページの「新規副腎不全診断バイオマーカーの同定」(資料のスクショ)には、副腎不全の診断に、コルチゾールの量ではなく、単核細胞の11β-HSD1という酵素の働きを使えるかもしれないという研究が書かれていました。
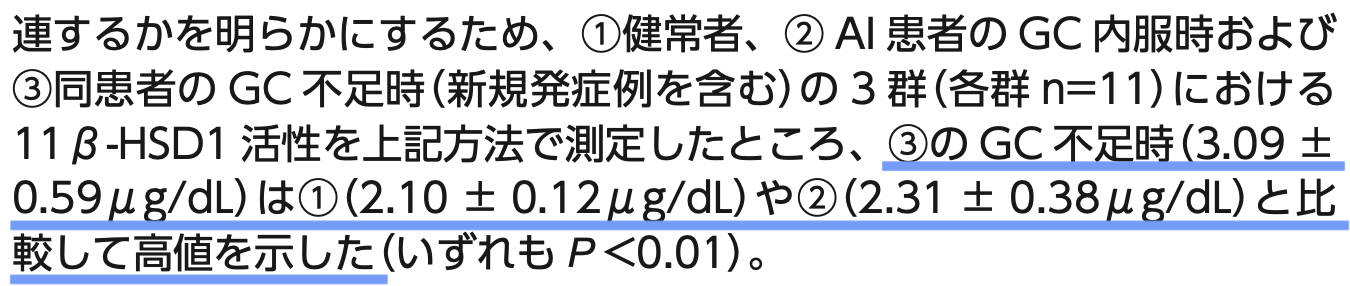
「11β-HSD1」という酵素は、体の中でコルチゾン(効かないホルモン)をコルチゾール(効くホルモン)に変える働きがあります。健康な人では11β-HSD1がよく働いているのに対し、副腎不全の患者ではその働きが弱くなっていることが分かったそうです。このことから、「コルチゾールの量」ではなく、「体の中でどれだけ働いているか(作用)」を見る指標として、11β-HSD1の活性が新しい診断マーカーになる可能性があると考えられました。
点眼ステロイド薬による副腎不全
資料の45ページの「点眼ステロイド薬による医原性副腎機能低下症」(資料のスクショ)には、ステロイド点眼薬でも、副腎機能が抑制されることがあるので、全身投与と同様に慎重な管理が必要という報告が書かれていました。
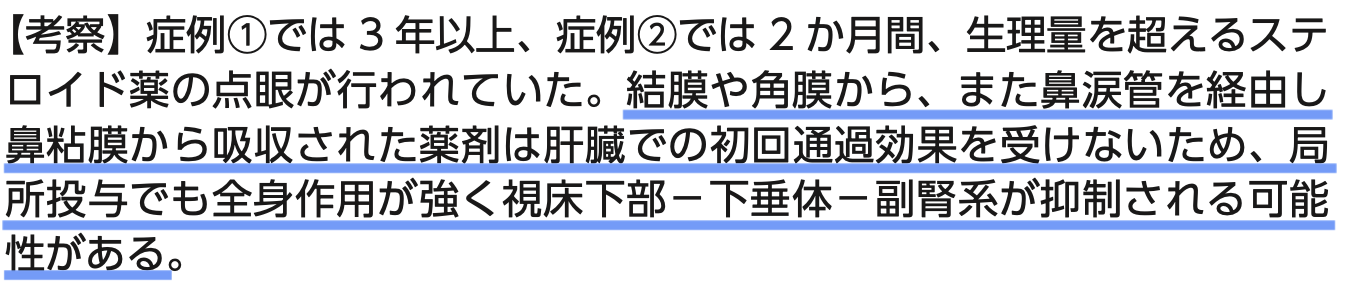
点眼薬は局所投与なので、全身への影響は少ないと思われていましたが、この症例では換算するとかなり高用量のステロイドになっていて、生理的分泌量を超えているというのは予想外でした。また、ベタメタゾン1mg=ヒドロコルチゾン30mgという換算比も衝撃で、点眼なのにこれだけ強力なステロイドが毎日体内に入っていた可能性がある、ということになります。
点眼薬として使用されたステロイドは、結膜や角膜からだけでなく、鼻涙管を経由して鼻粘膜からも吸収される可能性があります。これらのルートを通じて吸収された薬剤は、肝臓での初回通過効果(first-pass effect)を受けずにそのまま全身へ移行するので、全身へのステロイド作用が現れやすくなり、結果として、HPA軸(視床下部ー下垂体ー副腎)が抑制され、副腎機能低下につながるリスクがあるそうです。
LC-MS/MS(質量分析法)
今回の学会抄録では、ステロイドホルモンの精密な測定手法としてLC-MS/MSを用いた研究が複数見られました。特に、副腎ステロイド(コルチゾール・コルチゾン・DHEAなど)の同時定量やプロファイリングが可能なことから、副腎皮質機能低下症をはじめとする内分泌疾患の、より正確な診断や病態の把握に役立つ手法として注目されています。欧米ではすでに臨床導入が進んでおり、日本でも従来の免疫測定法(RIAやCLIA)では難しかった微量ホルモンの評価に、LC-MS/MSの導入が徐々に広がりつつある印象を受けました。
内分泌撹乱物質(EDCs)
今回の学会抄録では、「植物由来の天然エストロゲン」や「外因性エストロゲン」が、経路(経口・経皮)や代謝の違いによって内分泌系にさまざまな影響を及ぼす可能性があることにも触れられていました。また、内因性エストロゲン(体内で作られるホルモン)の状態によって、外因性エストロゲン(環境・食品・薬などから入ってくるホルモン様物質)の作用が、同じ物質でも「刺激する(アゴニスト)」側にも「ブロックする(アンタゴニスト)」側にも変わりうることが書かれていました。
少し前に欧米の情報として目にしていたしていた新しい検査方法のLC-MS/MS(質量分析法)が導入されつつある件や、内分泌撹乱物質の影響についての記述もあり、やはり欧米のコミュニティに情報に目を通しておくことで、日本での今後の動きの「前触れ」が見えると改めて実感しました。
出典
第32回日本ステロイドホルモン学会学術集会
https://www.jstage.jst.go.jp/article/endocrine/100/5/100_1449/_article/-char/ja/
副腎皮質機能低下症のメカニズムに関する情報は「Note」へ、補充療法のヒントは「Hint」へ、その他の情報は「Misc」へ、メッセージ経由でいただいた質問の一部は「FAQ」にまとめています。読んでくださった方が、自分なりの工夫を見つけるヒントになればうれしいです。
※体験をもとに整理した内容であり、医学的助言を目的としたものではありません。医療に関する判断を行う際は、必ず医師にご相談ください。
